相模原市周辺を中心に神奈川県や東京都で活動しています。
受付時間 | 平日8:00~18:00 ※土日祝日、夜間も可能(要事前予約) ※初回面談無料(1時間まで、オンライン・TELのみ) |
|---|
ZOOM等によるWEB面談も対応可能です。
小規模宅地等の特例 ~特定事業用宅地等についての注意点~(2021年9月12日)
相続税を抑えるために最重要となる特例の一つが小規模宅地等の特例です。小規模宅地等の特例は4種類ありますが、今回はそのうちの一つである特定事業用宅地等について解説します。
主に個人事業主の方が対象となりますので、該当する方はぜひご確認ください。
目次

小規模宅地等の特例は、まず4種類あることを抑えましょう。
小規模宅地等の特例とは、被相続人(お亡くなりになった方)が所有していた一定の土地について、一定の親族が相続で取得した場合に、土地の評価額を一定額減額する特例のことです。
「一定」という表現を3か所に使用しましたので、これだけではわかりづらいかもしれません。そこで、「一定」の内容について、もう少し詳しく次で解説します(※)
※ただし、小規模宅地等の特例は非常に複雑な特例であり、次の表もあくまで目安としてご利用いただき、詳細は税理士等に確認することをおすすめしています。
一定の土地
相続日時点で以下の用途に利用されていた土地が該当します。
| 種類 | 用途(利用形態) |
|---|---|
| 特定居住用宅地等 |
|
| 特定事業用宅地等 |
※事業には不動産賃貸事業等は含まれません。 |
| 特定同族会社事業用宅地等 |
※事業には不動産賃貸事業等は含まれません。 |
| 貸付事業用宅地等 |
|
被相続人が利用していた土地だけでなく、被相続人と「生計を一にしていた」親族が利用していた土地も該当します。
「生計を一にしていた」とは同じ生活単位であるということであり、同居していた親族と捉えれば大きく外れることはないでしょう(厳密には「同居」と「生計一」は別の考え方なので、あくまで大まかなイメージとして捉えてください)
特定居住用宅地等や貸付事業用宅地等については、次のリンク先の記事で詳細を解説していますので、よろしければそちらをご覧ください。
一定の親族
土地の種類ごとに次の条件を満たす親族が相続で取得した場合に特例の対象となります。
| 種類 | 親族 |
|---|---|
| 特定居住用宅地等 |
|
| 特定事業用宅地等 |
|
| 特定同族会社事業用宅地等 |
|
| 貸付事業用宅地等 |
|
上記の表に該当する親族がその土地を取得することのほかに、その土地を申告期限まで所有し続ける、申告期限まで住み続ける、事業を継続するといったことも基本的には必要になりますのでご注意ください(一部例外はあります)
特定居住用宅地等にある配偶者、同居親族、別居親族については、次のリンク先の記事で詳細を解説していますので、よろしければそちらをご覧ください。
一定の減額
土地の種類ごとに減額できる限度面積と割合が異なります。
| 種類 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等 | 330㎡まで | 80% |
| 特定事業用宅地等 | 400㎡まで | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡まで | 80% |
| 貸付事業用宅地等 | 200㎡まで | 50% |
なお、2種類以上を組み合わせて利用することもできます。例えば、特定居住用宅地等と特定事業用宅地等、特定居住用宅地等と貸付事業用宅地等のように組み合わせて利用することもできますが、併用する際に限度面積の調整計算を行う場合があります。
調整計算の考え方は次のリンク先の記事で解説していますので、よろしければそちらをご覧ください。

事業を営んでいる土地が対象になります。
今回のテーマである特定事業用宅地等についてですが、具体的には被相続人が事業を行っていた場所の土地、被相続人と生計を一にしている親族が事業を行っていた場所の土地が対象となります。
例えば、被相続人が個人事業主として小売店を経営しており、その小売店の土地を被相続人が所有していた場合に、その土地が対象になり得ます。
また、被相続人と生計を一にしている長男がスポーツジムを経営しており、そのスポーツジムの土地を被相続人が所有していた場合に、その土地が対象になり得ます。
そのような土地を取得した親族が、申告期限まで事業を継続して行い、その土地を所有し続けることで、土地(400㎡まで)の相続税評価額を80%減額することができます。
1億円の土地であれば、2,000万円(1億円-1億円×80%)で評価できることになります。相続税の税率は表面的には10%から55%なので、仮に税率が10%の場合は、土地の評価減額8,000万円の10%(=800万円)の相続税の減額につながります。
なお、被相続人や被相続人と生計を一にしている親族が行っていた事業が不動産賃貸事業などの場合は、特定事業用宅地等ではなく貸付事業用宅地等の対象になります。減額の割合等が異なりますのでご注意ください。
特定事業用宅地等についての税制改正が最近続きましたので、ここでは大きな改正を2つ紹介します。
特定事業用宅地等には、原則として相続開始前3年以内に新たな事業の用に供された土地は除かれます。
例えば、相続発生の1年前に被相続人が空き家であったご自身の土地の上の建物を改修し、新たに飲食業を開始した場合などは、基本的には特定事業用宅地等には該当しません。
ただし、例外が2つあります。
1つ目は、平成31年4月1日から令和4年3月31日までに発生した相続で取得した土地で、平成31年3月31日までに事業の用に供されていた土地です。
例えば、平成31年2月に飲食業を開始し、令和3年1月に相続が発生した場合は、相続開始の約2年前に新たに事業を開始していますが、この例外措置により特定事業宅地等からは除かれない、結果として特定事業用宅地等に該当するので、他の条件を満たせば小規模宅地等の特例が利用できます。
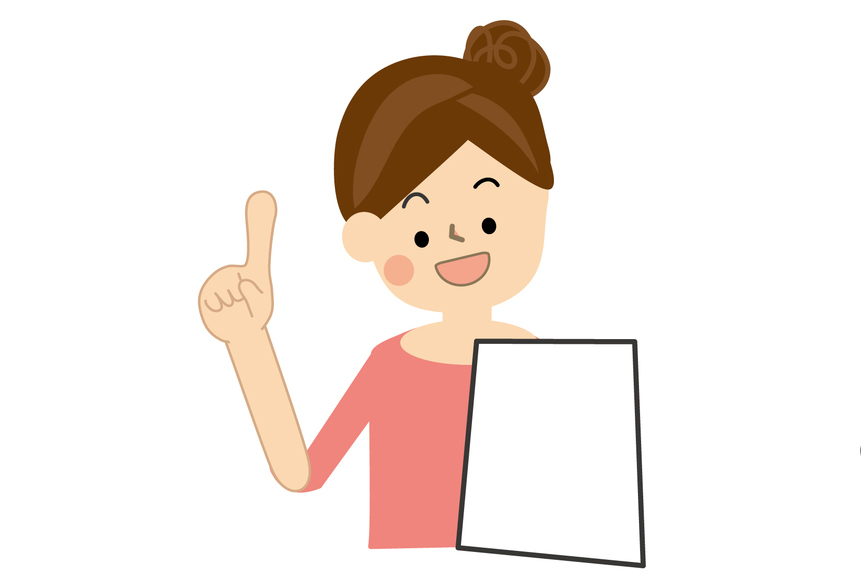
相続発生の時期と、新たに事業を開始した時期が重要になります。
2つ目は、新たな事業を一定規模以上で行っていた場合です。
一定規模以上になるかどうかの判定は、定められた計算式があるのでそちらに沿って判定することになりますが、大まかには新たな事業に使用されている事業用資産(建物、機械装置、器具備品など)の価額がその土地の価額の15%以上であることが求められます(具体的な計算は税理士等にご確認ください)
事業用資産の価額が15%以上であるということは、ある程度本腰を入れて事業を行っているということになります。
以前は、相続前に駆け込みでちょっとした事業を始めれば特定事業用宅地等の対象になり、特例の恩恵を受けられていましたが、そのような動きが目立ったのか、税制改正により原則として相続開始前3年以内に新たに事業を開始した土地は、特定事業用宅地等の対象外となりました。
ただし、新たな事業を一定規模以上で行っていた場合で、たまたまその後すぐに相続が発生した場合まで対象外とするのは特例の趣旨からも異なるということで、2つ目のような例外措置が定められたというわけです。
個人版事業承継税制について、ここでの詳細な説明は割愛しますが、平成31年から令和10年までに相続や贈与で個人の事業用財産(土地など)を引き継いだ場合に、一定の条件を満たすことで事業用財産に関する相続税や贈与税の納税を猶予する制度です。
事業を行っていた個人の方に相続が発生した場合は、条件を満たせば個人版事業承継税制も特定事業用宅地等の特例もどちらも利用できそうに思えますが、こちらは併用できないことが明確化されています。
どちらの制度の利用が有利かは、お客様の状況により異なりますので、個別に税理士等にご確認いただければと思います。
今回は特定事業用宅地等についての概要と税制改正の内容を解説しました。
個人事業主の方やそのご家族にとっては、重要な制度になります。税制改正により変更になっている箇所も多いので、以前に確認したという方も改めて確認することが必要かもしれません。
関連するその他の記事はこちらになります。よろしければご覧ください。
※できる限りわかりやすくお伝えすることを優先し、あえて詳細な説明は省略しております。そのため、実際の取扱いなどは別途ご確認くださいますようよろしくお願い致します。
お気軽にお問合せ・ご相談ください

| 受付時間 | 8:00~18:00 |
|---|
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
受付時間:平日8:00~18:00
※土日祝日、夜間も可能
(要事前予約)
※初回面談無料(原則1時間まで、オンライン・TELのみ)
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
