相模原市周辺を中心に神奈川県や東京都で活動しています。
受付時間 | 平日8:00~18:00 ※土日祝日、夜間も可能(要事前予約) ※初回面談無料(1時間まで、オンライン・TELのみ) |
|---|
ZOOM等によるWEB面談も対応可能です。
相続の場面における生命保険金の活用の
メリットについて(2020年8月19日)
相続に備えた生前の対策を考える場面では、生命保険の活用が一つの案としてよく登場します。今回は、生命保険の活用がなぜ生前の対策になるのか、以下のポイントに沿って説明していこうと思います。
生命保険を活用するポイント
-
相続税を計算するうえでの非課税枠
-
相続発生後に必要な資金や相続税の納税のための資金の確保

生命保険に対する税金は複雑ですが、
まずは基本が大事です。
相続税を計算するうえでの非課税枠
生命保険を契約する際には、登場人物として大きく3種類の人物を設定することになります。
①保険料負担者(契約者)、②被保険者、③保険金受取人の3者です。それぞれを誰にするかで、保険金を受け取ったときの税金のかかり方が全く異なりますので、まずは下の表(※)をご覧ください。
※下の表はあくまで一般的なものとなりますので、具体的な取扱いは別途ご確認くださいますようよろしくお願い致します。
| 保険料負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 | |
|---|---|---|---|---|
| パターン① | A | A | B | 相続税 |
| パターン② | B | A | B | 所得税 |
| パターン③ | A | B | C | 贈与税 |
相続税が発生するパターン①の保険というのは、大ざっぱに言えば、被相続人が自らかけた保険で被相続人の相続発生後に、死亡保険金が被相続人以外の方に支給されるタイプのものです。
支給された生命保険金は相続財産とされ、相続税の計算対象となりますが、一定の契約形態にて契約した生命保険金については、相続税を計算するうえでは一定額まで非課税となります。
一定の契約形態というのは、保険料負担者が被相続人、被保険者が被相続人、保険金受取人が相続人という契約形態のものです。保険料負担者は契約者となることが多いので、契約者が被相続人と説明されることも多いのですが、厳密には保険料負担者が被相続人であるものが対象になります。
この契約形態を満たす生命保険金を受け取った場合は、「相続人の数×500万円」までは相続税がかかりません。例えば、被相続人が父、相続人が母と子2人であったとすると、相続人は3人ですから、受け取った生命保険金のうち1,500万円までは相続税がかからないということになります。
それでは、この非課税枠を活用することで、税額がどのくらい変わるのでしょうか?
一つ事例を挙げますのでご覧ください。パターン①は被相続人の財産が預貯金のみで8,000万円、パターン②は被相続人の財産が預貯金6,500万円・生命保険金1,500万円となります(相続税の計算にあたり、配偶者の税額軽減は考慮しておりません)
| パターン① | パターン② | |
|---|---|---|
| 預貯金 | 8,000万円 | 6,500万円 |
| 生命保険金 | 0円 | 1,500万円 |
| 非課税枠 | 0円 | ▲1,500万円 |
| 財産合計 | 8,000万円 | 6,500万円 |
| 相続税の総額 | 350万円 | 170万円 |
パターン①のように、生命保険金に加入せず、相続を迎えた場合は相続税が合計で350万円発生します。
一方で、生前に手持ちの預貯金のうち、1,500万円を生命保険料として払い込み、ご自身の相続後に相続人が生命保険金として1,500万円を受け取れるタイプの保険に加入した場合がパターン②です。この場合の相続税は合計で170万円と半分以下に減少しています。
この生命保険金の非課税枠については、受取人が相続人であれば基本的にはどなたでも活用できるものですが、孫など相続人以外の方が受け取った場合には、非課税枠は使えませんのでご注意ください。
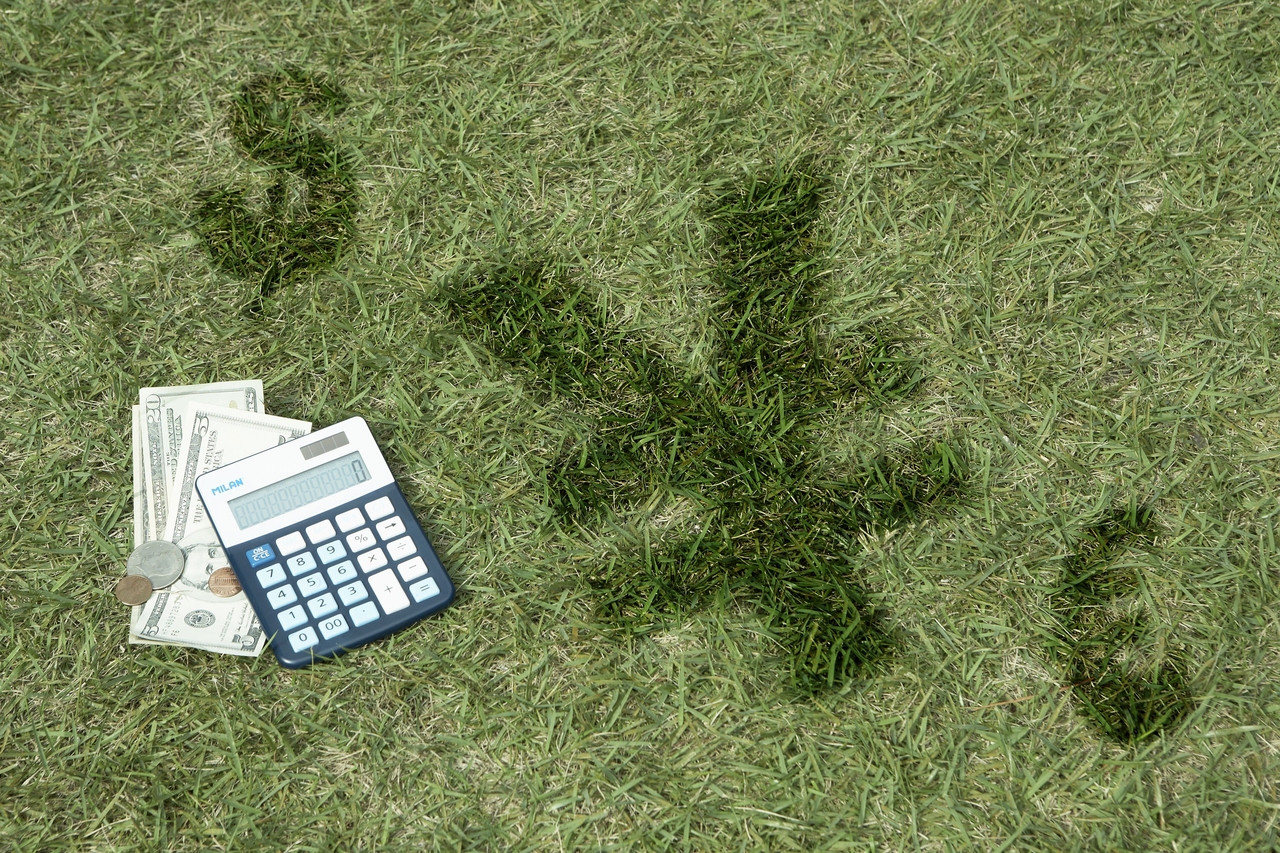
数字で見るとより生命保険の効果がわかります。
契約形態に気をつければ難しい対策ではなく、かつ相続税を減少させる効果も相応に見込めるものなので非常におすすめできる対策なのですが、実はこの非課税枠は意外に利用されていないというのが実感としてあります。
保険については、保険会社の営業が煩わしいといった保険嫌いの方もいれば、過去に大病を患っていたり、高齢なので保険の加入は無理だろうと保険の活用がそもそも選択肢になかったり、という方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、保険は進化しており、種類もかなり増えています。90歳まで健康状態の告知なしで加入できる保険もあります。
相続税の税率(表面税率)は最低でも10%ですから、生命保険金の非課税枠が1,500万円ある場合に、まったく活用しないのとフルに活用するのとでは、最低でも相続税に150万円(1,500万円×10%)の差が出てきます。
これまでにお手伝いさせていただいた相続税申告でも、生命保険金の非課税枠の活用をしておけば、相続税がかなり抑えられた若しくは発生しなかったのにと思った事例がいくつもありました。
もちろん、保険の活用は税金の問題だけではありません。手持ちの資金を保険料の払い込みで減らしてしまうと、今使えるお金を減らすことになってしまいますので、必ず活用してくださいと言うつもりはないのですが、手軽にできる対策の割に効果は大きいものだと思いますので、あまり考えたことがなかったという方は、一度ご検討いただく価値はあると思います。
相続発生後に必要な資金や納税資金の確保

遺されるご家族の負担をできるだけ
減らしましょう。
被相続人の預貯金は相続発生後に凍結されてしまい、遺産分割が確定するまでは、基本的には預貯金の引き出しができなくなってしまう(※)のですが、生命保険金の場合は保険会社に請求すれば、翌日から概ね1週間後までには保険金が振り込まれます。
相続後は、葬儀費用や病院代の支払など何かとお金が必要になるものです。また、相続税が発生する場合であれば、納税するためのお金も必要です。
相続人に負担をかけないように、あらかじめ生命保険金でそれらのお金を準備しておくことは、相続人の負担を軽くすることにつながり立派な生前対策になります。
(※)民法の改正により、2019年(令和元年)7月1日からは凍結された預貯金であっても一定額(1つの金融機関あたり最大150万円)までは相続人が払い戻しを受けられる制度が始まっていますので、この制度を活用し相続後に必要なお金を工面するのも一案かもしれません。払い戻しの制度の詳細は、法務省から公表されている以下のリンク先のパンフレットの3ページ目(右下にページ番号の記載がございます)をご覧ください。なお、閲覧にはPDFがご覧になれる環境が必要です。
http://www.moj.go.jp/content/001318284.pdf
終わりに
当事務所では、相続税の試算により、どのくらいの相続税が発生しそうか、また生命保険金の非課税枠を活用した場合にどのくらいの効果が見込まれるかなどをわかりやすくお客様にご説明致します。ご興味のある方はぜひお問合せください。
そのほかの関連記事はこちら
※できる限りわかりやすくお伝えすることを優先し、あえて詳細な説明は省略しております。そのため、実際の取扱いなどは別途ご確認くださいますようよろしくお願い致します。
お気軽にお問合せ・ご相談ください

| 受付時間 | 8:00~18:00 |
|---|
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。
お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約
受付時間:平日8:00~18:00
※土日祝日、夜間も可能
(要事前予約)
※初回面談無料(原則1時間まで、オンライン・TELのみ)
フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。
